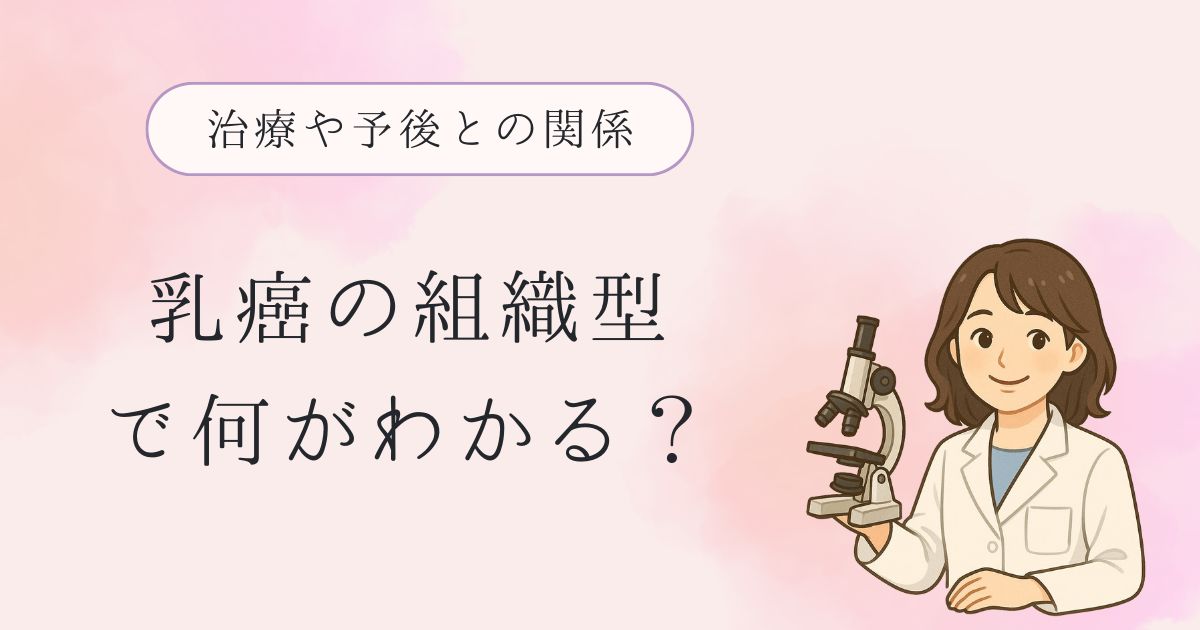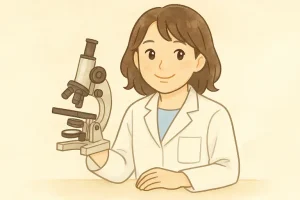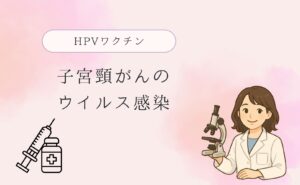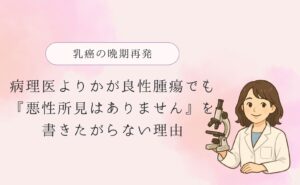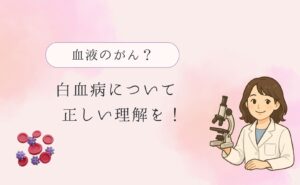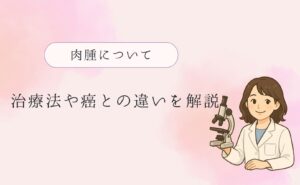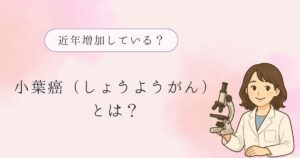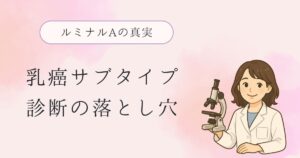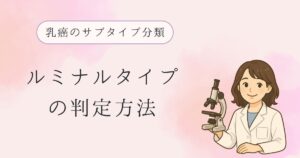胃から発生すれば胃癌、肺から発生すれば肺癌というように、癌は原発した臓器の名前で呼ばれます。
乳癌は乳腺から発生した癌です。
どの臓器にできた癌であっても、「組織型」と呼ばれる分類があります。
これは、癌がどのような形態や構造で増殖しているかを病理的に分けたものです。
 よりか先生
よりか先生ただし、この組織型の分類方法は臓器ごとに異なります。
胃癌・大腸癌・膵臓癌などでは類似した分類体系が使われることもありますが、完全に一致するわけではありません。
それぞれの臓器で特有の分類が存在し、それに応じて診断や治療方針が組み立てられます。
この記事では、乳癌における組織型の種類や分類方法について、実際の診療で使われている基準をもとに分かりやすく解説していきます。
日本の代表的な組織型(取扱い規約第18版)
乳癌の組織型は、日本独自の分類と、WHO(世界保健機関)による国際分類があります。
両者には重なる部分もありますが、細かい点では異なります。
日本では、「乳癌取扱い規約」という専門のガイドラインに基づいて分類が行われています。
長年にわたり第18版が使われてきましたが2025年6月末に最新の第19版が発刊され、分類や記載内容に一部変更が加えられました。



新しい規約の説明をするか迷ったのですが…
浸透には1年程度かかると考えられるため、今回は第18版に基づく分類を中心に解説します。
実際のところ現在、乳癌と診断されて情報を集めている方の多くは、第18版をもとに説明を受けているケースがほとんどだと思います。
そのため、これまで広く使われてきた第18版の分類を紹介しつつ、第19版で変更されたポイントもあわせてお伝えします。
浸潤性の乳管癌
まず、浸潤性の乳癌で一番多いのは乳管癌です。



浸潤についてはこちらの記事をお読みください。
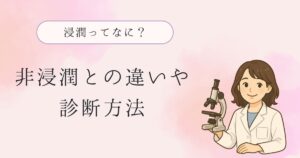
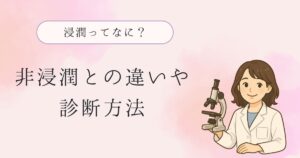
浸潤性の乳管癌は、以下の3つに分けられます。
- 硬型(scirrhous type)
- 腺管形成型(tubule forming type)
- 充実型(solid type)
| 型 | 英語表記 | 病理像の特徴 |
|---|---|---|
| 硬型 | scirrhous type | 線維化が強く硬い |
| 腺管形成型 | tubule-forming type | 細い腺管を形成 |
| 充実型 | solid type | 細胞がびっしり詰まる |
これらのタイプが混在していることもあるため、病理報告書には「硬型」が主体で「腺管形成型」も一部認められるといった記載がなされる場合もあります



病理医の好みにもよりますが、「sci>tub」みたいな感じです。
かつては、硬型が予後不良であると考えられていました。
しかし現在では、乳癌のサブタイプ(ルミナルAやHER2型など)による分類の方が、治療選択や予後予測において重要視されています。
また、硬型といっても、腫瘍細胞の核異型度(細胞の顔つき)によって性質は異なり、一概に「硬型=悪い」と判断することはできません。
そういった背景から、この分類自体の臨床的な意義は薄れつつあります。
実際、2025年に発刊された「乳癌取扱い規約 第19版」では、この分類(硬型・腺管形成型・充実型)は削除されました。



今後の病理診断では、これらの記載は見られなくなっていくと考えられます。
ただ、癌と正常な組織との境界は硬型のほうが充実型よりも不明瞭なことが多いため、部分切除を行った場合、硬型のほうが断端陽性となる割合が高い印象があります。
断端陽性とは、手術で切除した組織の切り口に癌細胞が残っている状態のこと
浸潤性乳管癌以外
乳管癌以外の癌はたくさんあります。
その中でもよくみるのは小葉癌で、あとは粘液癌や化生癌やアポクリン癌、浸潤性微小乳頭癌などです。
頻度は低いものの、臨床的に注目される型を並べました。
- 浸潤性小葉癌 多巣・両側性に注意
- 粘液癌 粘液プールが目立つ
- 化生癌 上皮‐間葉転換像を示す
- アポクリン癌 好酸性顆粒状細胞質
- 浸潤性微小乳頭癌 リンパ節転移が起こりやすい



これらの癌の特徴についてリクエストがあれば、また詳しく書かせていただきます。
組織型と予後は一致するとは限らない
患者さんからは「どの癌型がまだましなのか?」「予後の良い型はどれか?」といった不安の声をよく耳にします。
教科書的には以下のような傾向が記載されています。
- 粘液癌 → 予後が比較的良好とされる
- 化生癌・アポクリン癌 → 予後不良の傾向
- 浸潤性微小乳頭癌 → リンパ節転移を起こしやすい
ただし、粘液癌が必ずしも予後良好とは限りません。
リンパ節に転移していたり、乳房内に広く存在することもあります。
また、化生癌の中にも比較的経過が穏やかなタイプがあり、浸潤性微小乳頭癌であってもリンパ節転移を伴わない例もあります。
まとめ
組織型は、乳癌の性質を理解するための基本となる分類です。
ただし、「○○型だから必ず予後が良い」「△△型だから治療が難しい」といった判断は、必ずしも当てはまりません。
近年の治療方針や予後予測では、ホルモン受容体の有無、HER2の発現、Ki-67値、さらには遺伝子変異といった分子レベルの情報がより重視されています。
組織型ごとの傾向は参考になりますが、それだけにとらわれない視点も大切です。