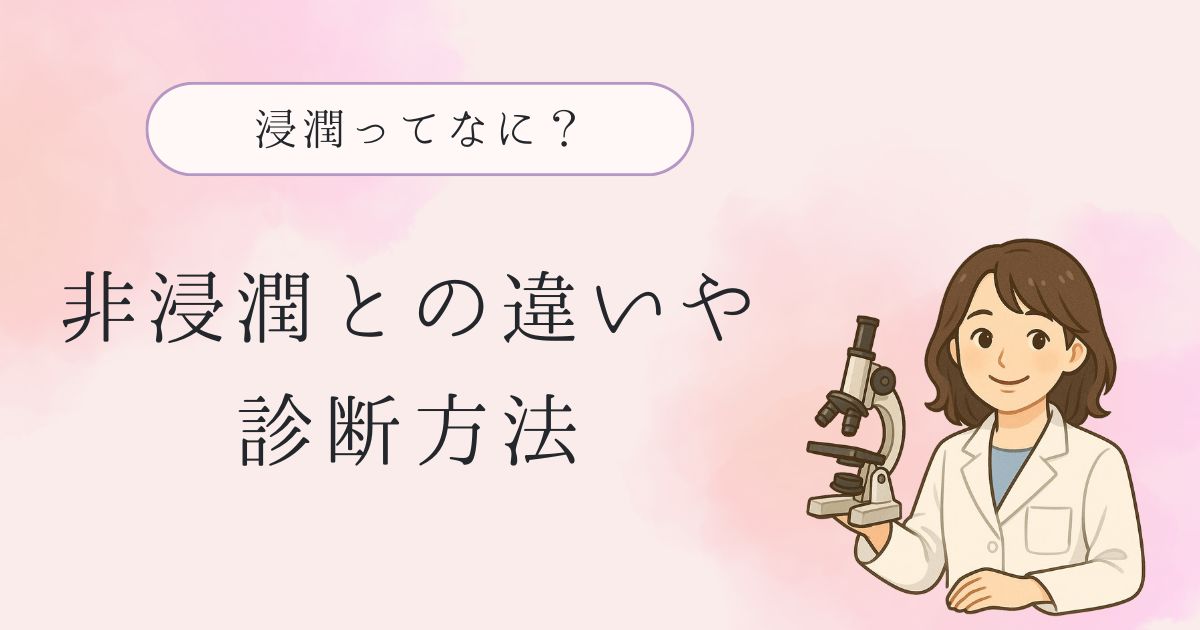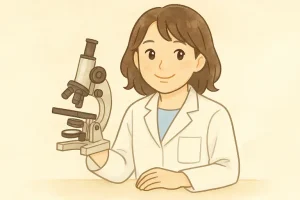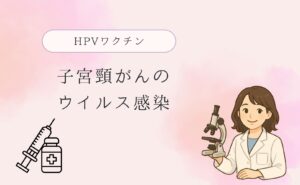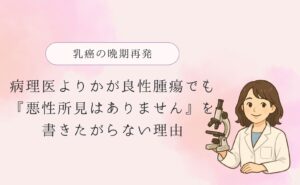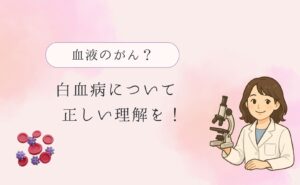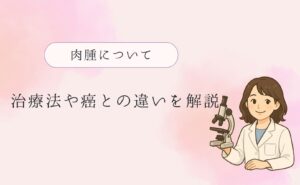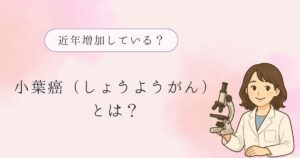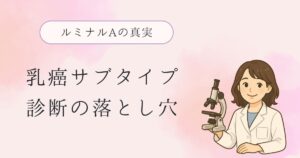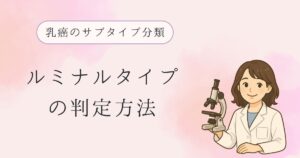「浸潤」という言葉を、検査結果や診断書などで目にする機会があるかもしれません。
浸潤があるかどうかは、癌治療の進め方やその後の経過に大きく関わる大切なポイントです。
この記事では、非浸潤と浸潤の違い、病理医がどうやって診断しているのかについてわかりやすくお伝えします。
浸潤とは
「浸潤(しんじゅん)」とは、癌細胞が周囲の組織の中にじわじわと入り込んでいく現象を指します。
 よりか先生
よりか先生癌が境界を越えて、周囲にしみ出すように進んでいくイメージです。
癌細胞が粘膜や乳管など本来の構造の内側に限局している場合は、周囲の組織には広がっていない状態とされます。
そこから外側の構造に踏み込んでいくと、「浸潤がある」とされ、癌の性質が一段階進んだことを意味します。
なお、「浸潤」は「転移」とよく混同されますが別物です。
浸潤は周囲の組織への直接的な広がりであるのに対し、転移は血液やリンパの流れに乗って離れた臓器に新たな癌が現れることです。
浸潤癌と非浸潤癌
癌は、浸潤の有無によって浸潤癌と非浸潤癌の2つに分けられます。
浸潤癌
基底膜を破って外へ出た癌細胞が、周囲の組織や血管・リンパ管に入り込みます。
この状態は「進行癌」とされ、転移や再発のリスクが高くなります。
非浸潤癌(上皮内癌)
癌細胞が乳管や小葉などの構造内にとどまっており、周囲へ広がっていません。
転移の可能性は極めて低く、切除で治療が完結することがほとんどです。
この段階で見つかれば「早期癌」に分類されます。
非浸潤癌は英語では以下のように表記されることがあります。
- Ductal carcinoma in situ(DCIS)
- Non-invasive ductal carcinoma
いずれも、「in situ(原位置の)」「non-invasive(浸潤していない)」という語が使われており、浸潤がない=周囲に広がっていない状態を意味します。
乳癌領域では、intraductal carcinoma(乳管内癌)という表現も、非浸潤癌を指す場合に使われます。
病理医はどうやって浸潤を判断している?
非浸潤癌は基本的にすべて早期癌、浸潤癌でも早期に見つかれば早期癌として扱われます。
「浸潤=進行癌」とは限らず、「浸潤はあるけど早期癌」というケースも多くあります。



例えば、浸潤のある乳癌でも1cm以下、転移なしなら早期癌(ステージI)です。
浸潤かどうかの判断は、次のような視点で行われています。
- 正常な構造をがん細胞が壊しているか
- 本来あるべき構造が、癌の部分には見られないか
例えば乳癌なら、乳管の外側にある「筋上皮細胞」が失われていれば浸潤と診断されます。
胃癌や大腸癌なら、粘膜構造の一部である「粘膜筋板」を超えていれば、そこから浸潤癌と見なされます。
筋上皮細胞とは 乳管や小葉のまわりに存在する薄い筋肉のような性質を持った細胞
粘膜筋板とは 胃や大腸の粘膜に存在する薄い筋肉層で、粘膜とその下の層(粘膜下層)を隔てる構造
乳癌の診断では、癌細胞の周囲に筋上皮細胞が存在するかどうかを確認します。



これは、浸潤があるかどうかを判断するための大切なポイントです。
まずは「HE染色(エイチイーせんしょく)」という、病理診断で最も基本的な染色方法を用いて観察します。
この方法で筋上皮細胞の有無がはっきりすれば、そこで診断は確定します。
ただし、構造がはっきり見えない場合もあります。
そのときは、「免疫染色」という特殊な染色を追加して、筋上皮細胞を特定します。
組織診断報告書に「免疫染色にて」「免疫組織化学検査にて」などと記載されていれば、通常よりも詳しい検査を行ったということです。
その分、窓口での支払いも少し高くなります。
ちなみに…免疫染色をどれだけやっても、病理医の手元に報酬は入りません。



この話はまた別の機会にでも…
まとめ
早期癌の中でも、非浸潤癌・上皮内癌の段階で見つかったならとても幸運なことです。
検診を受けていたとしても、必ずその段階で見つかるとは限りません。
癌のなかには、すごいスピードで進行するタイプもあれば、ゆっくりと時間をかけて成長するタイプもあるからです。
特に乳癌では、急激に増殖するタイプを小さいうちに捉えられるかどうかが重要です。
そのためには、定期的な検診に加えて、セルフチェックの習慣が欠かせないと言えるでしょう。



セルフチェックについては、また改めてご紹介しますね。