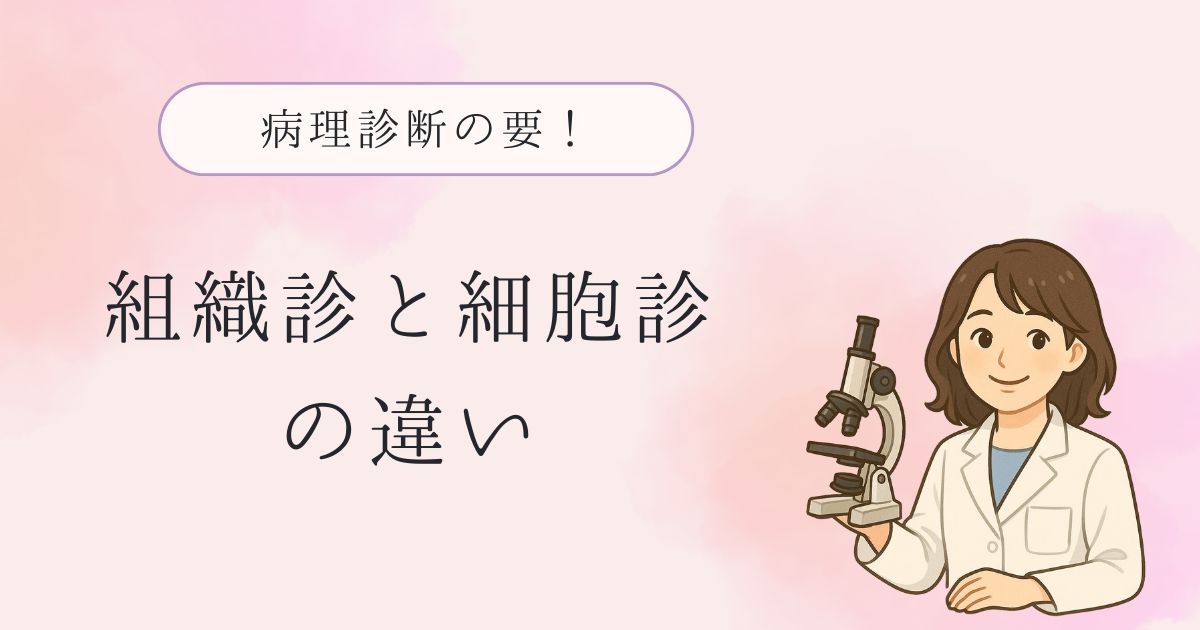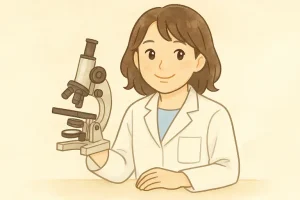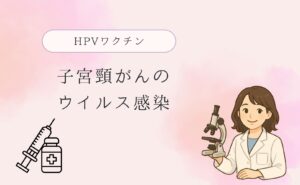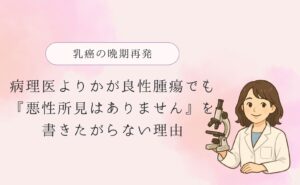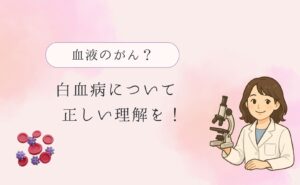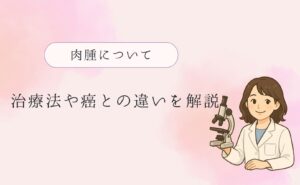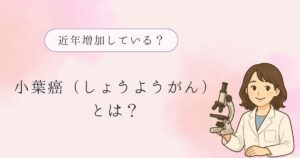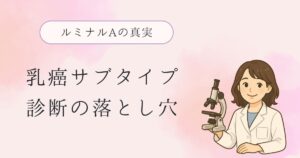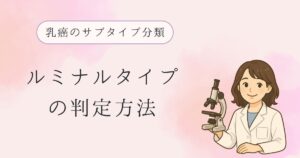乳房の検査では、細胞診と組織診という2つの方法が使われます。
 よりか先生
よりか先生どちらも病理診断の根幹を支える重要な検査です。
細胞診には、こすって採る方法、針で吸引する方法、尿や痰など自然に排出されたものを調べる方法など、さまざまな種類があります。
組織診も、内視鏡下での採取や手術時の切除など、状況に応じて検体の取り方が異なります。
今回はその中でも、「乳房に針を刺して行う細胞診」と「乳房の組織を採取する組織診」にしぼって、それぞれの違いを解説します。
細胞診と組織診の比較
細胞診と組織診の比較です。
費用比較
乳房の検査においては、細胞診の方が組織診よりも安価です。
おおよその目安として、組織診は細胞診の2倍から2.5倍程度の費用がかかるとされています。
これは、組織診の方が工程が多く、検査技師の手作業も多く必要となるためです。
プレパラート作成にかかる時間も長く、処理に使う設備や材料も細胞診より複雑です。
検体採取の流れ
乳房の細胞診・組織診は、どちらも針を刺して検体を採取します。
ここでは、それぞれの検査方法について具体的な工程を紹介します。
乳房の細胞診
細胞診では、細い針を使ってしこりの一部を吸引し、細胞を取り出します。



針が細いため、通常は麻酔を行いません。
採取した検体は、スライドガラス(プレパラート)上に直接展開し、次の手順で処理されます。
- スライドガラスに検体を出す
- もう1枚のスライドガラスで押し広げ、細胞を薄くする
- 固定液で細胞を保存する
- 染色して観察可能な状態にする
細胞を薄く伸ばすのは、細かな構造を顕微鏡で正確に観察するためです。
乳房の細胞診では、このとき作成したプレパラートが診断材料のすべてになります。
特殊な保存処理をしていない限り、あとから複製や追加染色を行うことはできません。
なお、まれに乳頭から自然に分泌された液体(血液や黄色い液体など)を細胞診に用いるケースもあります。
組織診の検体採取方法
組織診では、細胞診よりも太い針を使用し、しこりの一部を組織ごと採取します。



採取時には痛みが伴うため、局所麻酔を行うのが一般的です。
採取された組織は、以下の工程でプレパラートに加工されます。
- ホルマリンで固定し、腐敗を防ぐ
- 必要な部位を切り出す(特に手術検体では病理医が関与)
- 脱水・脱脂処理を行う機械にかけ、一晩処理
- パラフィンブロックに包埋し、冷却して固める
- ミクロトームで髪の毛より薄くスライス
- スライドガラスに乗せ、染色して完成
③(機械処理)と⑥(染色)を除く大部分は、検査技師による手作業が必要です。
そのため工程数が多く、時間や人的コストもかかります。
違いのまとめ
細胞診と組織診は、同じ「病理診断」のための検査でも、見え方に違いがあります。
例えるなら、細胞診は「みかんの房の中身」をプレパラートで押しつぶして観察するイメージ。
一方、組織診は「みかんが入った寒天ゼリー」を薄くスライスして断面を観察するようなものです。



構造の一部だけを見て判断するのが細胞診、周囲のつながりごと観察するのが組織診と言えます。
いずれも、血液検査のように機械にかけてすぐ結果が出るわけではありません。
検体が採取されてから、病理医のもとでプレパラートが完成するまでには一定の工程と時間が必要です。
プレパラートが早く仕上がるのは細胞診です。
検体の量も少なくて済み、麻酔をせずに実施できるという患者への負担の少なさが大きなメリットです。
一方、組織診では検体をしっかり加工するため、免疫染色による追加検査が可能になります。
乳癌の診断では、エストロゲン受容体(ER)・プロゲステロン受容体(PgR)・HER2・Ki-67など、サブタイプを判断するための免疫染色が必要になる場面が多く、これは組織診でなければ行えません。
良性か悪性かの判断が難しい場合も、追加染色を行える組織診の方が診断の信頼性が高くなる傾向があります。
細胞診と組織診にはそれぞれ利点があり、目的や状況に応じた使い分けが非常に重要です。



乳房以外にも、細胞診にはさまざまな種類がありますが、それについてはまた別の機会にお話しします。
まとめ
細胞診と組織診は、いずれも病理診断に欠かせない検査方法です。
どちらを選ぶかは、しこりの性質や大きさ、必要な診断精度、患者さんの負担など、さまざまな要素を考慮して決められます。
細胞診は、負担が少なく結果が早く出やすい反面、情報量には限りがあります。
一方で組織診は、検体処理に時間と手間がかかるものの、診断の精度が高く、追加検査にも対応しやすいという強みがあります。
主治医から説明を受けた際、「なぜこの検査なの?」と疑問に感じたときには、ぜひ今回の内容を思い出してみてください。