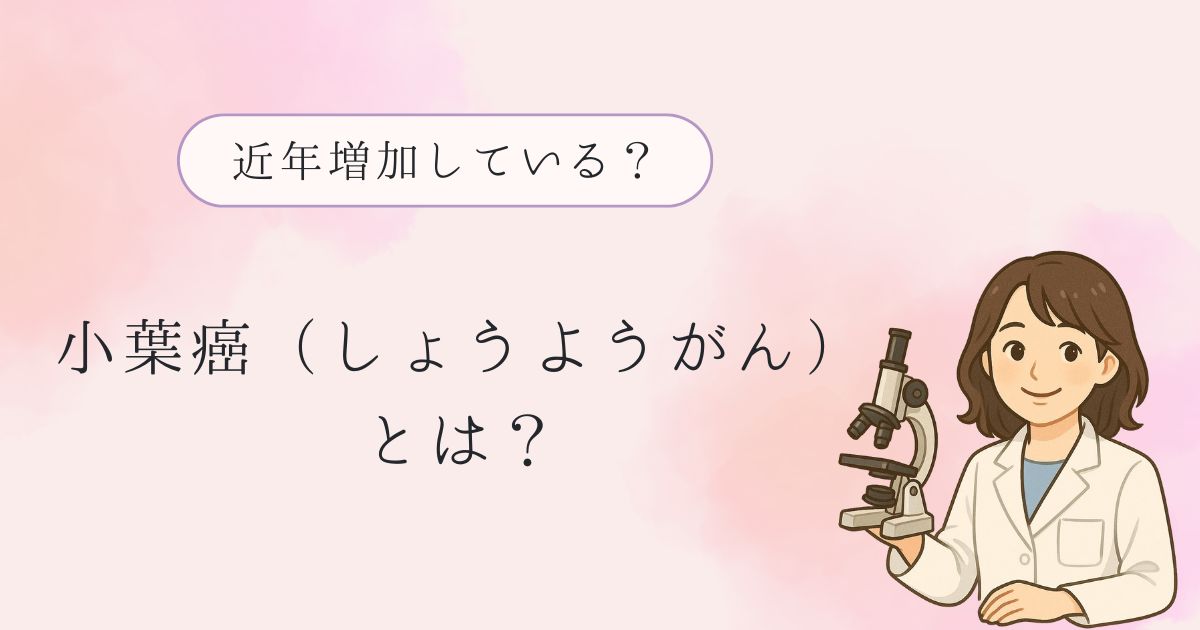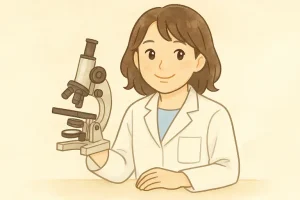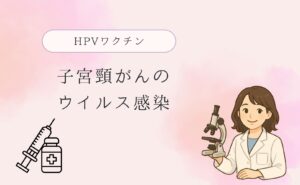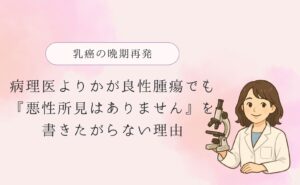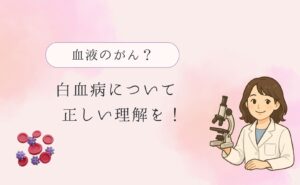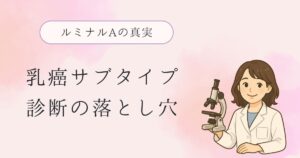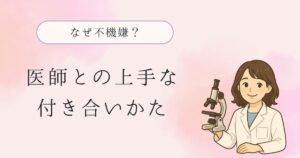乳がんの種類のひとつに小葉癌があります。
乳房特有の癌で、他の臓器には小葉癌という概念は存在しません。
乳がんの大部分は乳管癌であり、小葉癌は珍しいと紹介されることもあります。
ただ、普段から診断している私の印象では稀とも言えず、乳管癌よりは少ないにしても普通に見られる癌です。
 よりか先生
よりか先生それに、近年増加傾向にあるとされているんです。
小葉癌の特徴
基本的に癌細胞は、細胞と細胞がくっついているという点が、リンパ腫や肉腫と違う点(病理的に区別するのに用いる点)です。



肉腫についてはこちらも参照してください。
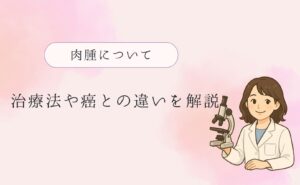
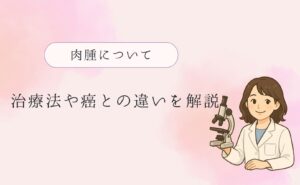
細胞接着因子「E-カドヘリン」
細胞同士を結びつける働きを担うのが、細胞接着因子の一つであるE-カドヘリンです。
小葉癌では、このE-カドヘリンの発現が欠如しているか、著しく弱くなっているのが特徴とされています。
病理診断では免疫染色という手法を用いて、この変化を確認します。
浸潤性・非浸潤性
小葉癌も乳管癌と同じように、浸潤性と非浸潤性に分類されます。
浸潤性小葉癌は周囲の組織へ広がる性質を持ち、非浸潤性小葉癌は乳腺の小葉内にとどまるタイプです。
さらに、癌とまでは言えないものの、小葉系の異型細胞が増える病態として異型小葉過形成(ALH)が知られています。
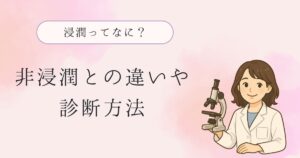
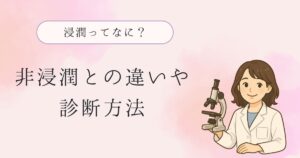
発生・転移の傾向
小葉癌にはいくつか特徴的な発生・転移の傾向があります。
- 両側乳房に発生しやすい
- 手術から5〜10年以上経過して再発する晩期再発がみられる
- 肝臓・肺・脳といった典型的な乳癌の転移先ではなく、消化管や卵巣などへの転移



私が実際に目にしたことがあるのは、卵巣、胃、小腸、十二指腸です。
近年の研究では、転移は癌細胞単独ではなく、その周囲の腫瘍間質も一緒に移動しているのではないかと考えられています。
癌細胞を「種」、間質を「土」とすると、種だけが飛ぶのではなく土も一緒に移動し、他の臓器で新たな環境を作って増殖していく、という仕組みです。
小葉癌の場合、この「土」が消化管や卵巣・子宮といった臓器に定着しやすいタイプなのかもしれません。
小葉癌の分類
小葉癌は性質の違いによっていくつかのタイプに分けられます。
ここでは、治療方針に関わるサブタイプと、病理診断で用いられる顔つきによる分け方について解説します。
サブタイプ分類
小葉癌の多くはホルモンレセプター陽性・HER2陰性にあたりますが、一部にはトリプルネガティブやHER2陽性も含まれます。
サブタイプはホルモン療法や分子標的治療の適応に関わり、治療方針や再発リスクの評価にも影響します。
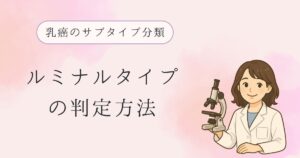
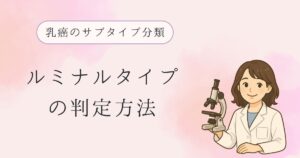
癌細胞の顔つきでの分類
また、小葉癌も、癌細胞の顔つきでの分類があり、古典型と非古典型に分けられます。
古典型
古典型では細胞の核は大きくなく、一見あまり悪そうに見えないのが特徴で、実際の診断では最も多くみられます。
非古典型
非古典型は予後不良な傾向があり、トリプルネガティブやHER2陽性にあたることが多いとされます。



さらに非古典型は充実型と多形型に分けられます。
充実型は小葉癌に特徴的な「ばらばらとした浸潤」ではなく、ある程度のかたまりを作って増殖するタイプですが、細胞と細胞の接着性が弱いという小葉癌の基本的特徴は保たれています。
多形型は細胞の異型が強く、核分裂像が多い点が際立っています。
診断・治療における注意点
切除
小葉癌は細胞と細胞の接着性が弱く、乳房内でバラバラに浸潤することがあります。
そのため、部分切除を選択する際は、特に慎重にならなくてはなりません。
また、画像では見えない範囲に浸潤が及び、断端に癌が出てしまうこともあります。
海外では部分手術の検体で非浸潤・古典型であれば、断端に出ていて取り残しの可能性があったとしても、追加切除を行わないとされています。
化学療法
化学療法の効果についてですが、小葉癌では癌が完全に消える「完全奏効(pCR)」になる確率が、乳管癌よりも有意に低いとされています。



つまり、小葉癌は乳管癌と比べて化学療法だけで治る可能性が低いということです。
とはいえ、化学療法が意味を持たないわけではありません。
治療後に癌細胞の密度を下げ、量を減らすことが予後を左右すると考えられており、小葉癌でも再発リスクの軽減や治療効果の向上につながります。
診断
小葉癌が「病理医泣かせ」といわれるのは、癌細胞が小さく、線維化の中にぱらぱらと少量存在することがあるためです。
生検やセンチネルリンパ節で見落としやすく、化学療法後の手術検体ではリンパ球との判別が難しい場合もあります。



このようなときには、免疫染色を追加することで診断精度を高めます。
また、小葉癌ではアポクリン分化という細胞の変化が起こることがあります。
この変化によって異型が弱く見えたり、逆に強く見えたりして診断が揺れる要因となります。
アポクリン化生ではエストロゲン受容体が陰性となり、代わりにアンドロゲン受容体が陽性になるのが特徴です。
この変化は小葉癌だけでなく乳管癌にもみられる現象です。
このように、小葉癌の診断には慎重さが求められ、病理学的な特徴を踏まえた多角的な評価が不可欠です。
患者さんにとって大切なポイント



最後に患者さんにとって大切なポイントです!
手術方法の選択について
部分切除か全摘出かを選べる場合は、慎重に検討することが大切です。
画像検査で確認できる範囲よりも実際の病変が広がっていることや、主病変から離れた場所にも複数の癌が存在する可能性があるためです。
転移の特徴について
小葉癌は一般的な乳癌とは異なる転移パターンを示します。
通常の癌では胃への転移は稀ですが、小葉癌は消化器系(胃、腸など)や婦人科系(卵巣、子宮など)の臓器に転移しやすい特徴があります。
そのため消化器科や婦人科での検査を受ける際は、担当医師に以下の点を必ず伝えましょう。
- 自分が乳癌の中でも「小葉癌」であること
- 小葉癌は生殖器や消化管に転移する可能性があること
- 転移の有無を確認するための検査であること
同じ病院内であっても、検査を担当する医師が必ずしもあなたの病歴を詳しく把握しているとは限りません。
ひとこと言う事で、検査を行う医師も、気合をいれて見てくれるはずです。



私は必ずそうします。
まとめ
小葉癌は近年増加が報告されており、臨床現場でも珍しくない乳癌です。
診断や治療の難しさはあるものの、腫瘍間質の研究など新たな知見が積み重ねられています。
治療面ではホルモン療法をはじめ有効な手段があり、適切に行えば十分な予後が期待できます。
化学療法では癌細胞を完全に消すことは難しくても、密度を下げ量を減らすことが大切です。
小葉癌は通常と異なる場所に転移しやすい性質を持つため、消化器系や婦人科系の検査も意識して受けましょう。